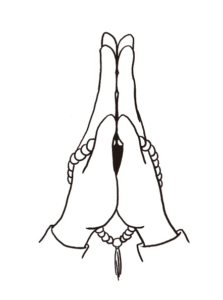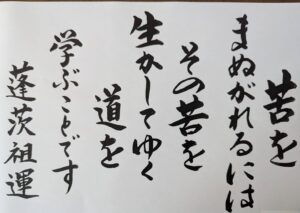住職の法話 第19回 法名
本日は法名のお話しです。皆さん一般的には「戒名」の方が聞いたことあると思います。
宗派によって言い方が違います。
浄土真宗では「法名」、日蓮宗では「法号」といい、その他の宗派は概ね「戒名」と言います。いずれも意味としては仏弟子になると言うこと。つまり仏教徒となると言う意味です。
時々、誤解されているのは戒名などは亡くなってから付けるものだと思っている方がいます。実際、亡くなってから付けると言うケースが多いのも事実です。なので、生前戒名をもらったなどと言うととても珍しいと思われます。
皮肉な事ですがキリスト教で考えると皆さん納得されるのですが、
クリスチャンの場合は赤ちゃんが産まれると教会に行って洗礼を受けてクリスチャンネームをもらいます。仏教も本来ならそれと同じで子供が出来たらお寺で授戒会(じゅかいえ、戒名の場合)や帰敬式(ききょうしき、浄土真宗)を受けて戒名や法名を授かるのですが、日本の場合は家ごとに宗派が異なります。ですから浄土真宗の家の子供が日蓮宗の家の方と結婚すれば浄土真宗または日蓮宗のどちらかを選ばなければなりません。本来なら家と言う単位ではなく個人で宗派を選んでも良いはずなのですが、やはり長年の家長制度に従って同じ家族は同じ宗派とならざるを得ないのが現状です。まぁ、お墓の事を考えると同じ宗派に統一せざるを得ない訳ですね。
ですから、日本では生前戒名や生前法名をもらうなら新しく結婚や養子に行くなどの姓が変わる可能性がある場合はやめておいた方がいいとなります。私は、本来年齢は関係ない訳ですが、その後の人生において新たに姓が変わる可能性がなくなれば生前で頂くことをお勧めしています。ですから、概ね還暦を過ぎたら頂くのがよろしいかと思います。
そもそも、俗名で葬儀を仏式で行うと言うのは本来ならあり得ないのです。仏教徒だから仏式で葬儀をするのです。ですから法名なんか要らない、戒名なんか要らないと言う方は「無宗教」で葬儀をするべきなのです。しかし、やはり日本では死んだら僧侶を呼ぼうとなる訳ですね。
現状ではお寺としては本来認められないのだけれども俗名で仏式葬儀をするケースもあります。但し厳しい住職の場合は戒名無しでは葬儀は受けませんと言うお寺も実際にあります。
次にひと口に戒名と言っても実は細かく分類されています。
一般的な戒名は6文字が多いですね、○○○○信士とか信女ですね。この6文字の最初の2文字を「道号」と言います。そして次の2文字を「法名」と言います。そして最後の「信士」を信士号、女性であれば信女号となります。この六文字をひっくるめて戒名と言います。それから更に○○院と言うのも有りますね。これは「院号」と言います。皆さんが良く聞く話としては「院号」付いてるから高いよね、なんて話が出ます。
そもそも院号というのはその家が決まった菩提寺があって、先祖代々の付き合いがありそのお寺の為に例えば本堂の畳を貼り替えたり屋根の瓦を葺き替えたりしてくれたお礼に寺から出すのが本来の院号です。つまりお寺に対して貢献度がある方にお寺が感謝して出すのです。だから由緒あるお寺ではいくらお布施を積んでも貢献度の実績が無ければ院号は付けません。それが時代とともに変化してたくさんのお布施をすればそれが貢献度になるから院号を出しましょうと変化して来たのです。ですから院号というのは偉いからとか金持ちだからとかそう言う理由で付けるものではなく、あくまでもその寺に対する貢献度があるか無いかでつけられるのです。だから院号は名誉称号と考えてください。但し日本では戦争に行った兵隊さんには日本の為に尽くしたと言う理由で多くの寺が院号を出したと言う歴史があります。だから昭和20年頃には院号がやたらと増えたのです。
まぁ、一般的にはお父さんが院号付いてるからお母さんも付けてもらわなきゃなんて話で院号を希望する方も多い訳ですけどね。
ちなみに浄土真宗では基本的な法名は釋○○と3文字です。
これは東本願寺でも西本願寺でも同じです。
昔は女性だけ「尼」と言う字が入りました。
それも小さく尼を書きます。理由は他宗さんは信士とか信女が付くから男性か女性か分かるけれど浄土真宗ではそれが無い(例外的に浄土真宗でも信士信女居士大姉を付ける寺もある)ので、男女が分かるように「尼」が入りました。まぁ、仏門に入って尼さんになると言う意味です。しかしね、仏様って性別無いんですよ。だから区別する必要なんてそもそも無いんですよ。だから現在の真宗では東西を問わずに釋○○となります。
ただね、先に亡くなったお婆ちゃんとかに尼が付いてると合わせて付けたいと言われる方も居ますのでね、うちの寺では臨機応変に対応しています。
ですから、浄土真宗では3文字なので他宗さんのように道号とかはありません。なので法名だけなのです。
但し、浄土真宗でも高田派だけは道号と信士号信女号が付きます。
なので釋○○○○信士のようになります。何故なら高田派は浄土真宗の中で1番古い宗派で天台宗の影響を受けているからです。東西本願寺よりもずっと古いのです。
さて、浄土真宗では何故法名と言うかをお話しします。そのためには戒名の話をする必要があります。戒名とは文字通り仏教徒として守るべき「戒」を授けた者にその証として戒名を授与します。
仏教徒が守るべき戒とは五つあります。
①不殺生戒(殺さない)
②不妄語戒(嘘をつかない)
③不偸盗戒(盗まない)
④不邪淫戒(淫らな事をしない)
⑤不飲酒戒(酒を飲まない)
と言うものです。
この中ではやはり1番重たい戒は①の不殺生戒ですね。しかし、私たち人間は生まれてからずっと殺生をせずには居られないのです。何故なら食べるものは全て動植物の命ですから。親鸞聖人はとても合理的な考えのお方でした。
守れないような戒を授けるのはいかがなるものかとお考えになったのです。
と言う事から浄土真宗では授戒をしません。戒を授けないのだから当然戒名も無い訳です。
そのかわりに法名を付けます。「法」とは仏法僧と言う言葉がある通り仏様の教えを指します。つまり法名とは仏様の教えに従う者に付ける名前となります。
ちなみに、「門徒モノ知らず」なんて言葉があります。門徒とは浄土真宗の信者の事です。
これは浄土真宗の教えは善悪を問わず必ず阿弥陀如来の本願力によって私たちは極楽浄土に救われると言う教えから、俗信や迷信を信じないので、例えば葬儀に行ったら家に入る前に清め塩を使うなど、世間で一般的になされている事をしないのに対して揶揄された言葉です。
また、本願ぼこりと言う言葉もあります。浄土真宗では悪人でも救われると言う教えから敢えて悪事を働くことを指します。しかし、親鸞聖人は「解毒剤があるからと言って自ら毒を飲むような真似はいけない」と戒めておられます。
これらは戒が無いから何をしても良いのだと言うところから来ているようです。
親鸞聖人は決してそうではない、仏教徒として守るべき戒は極力守るべきだとお考えなのです。
お釈迦さまのお言葉も引用されてます。「少欲知足」であれと。
さて法名とは何か判ってスッキリしましたね。
いつものようにお念仏をしましょう。なんまんだぶ、なんまんだぶ、なんまんだぶ。合掌